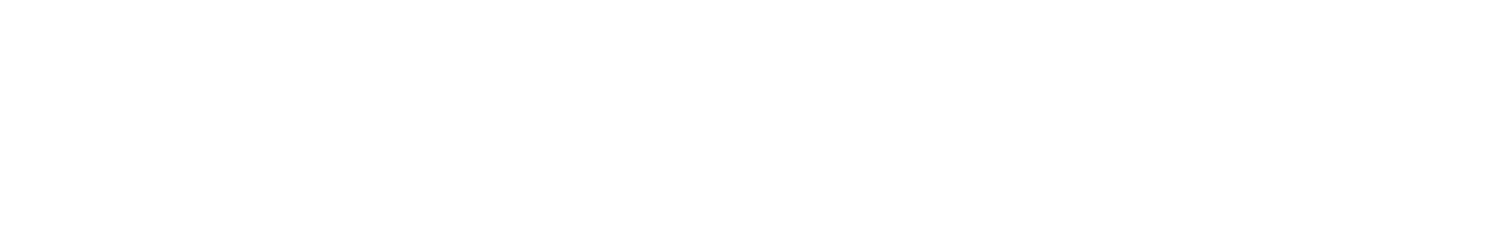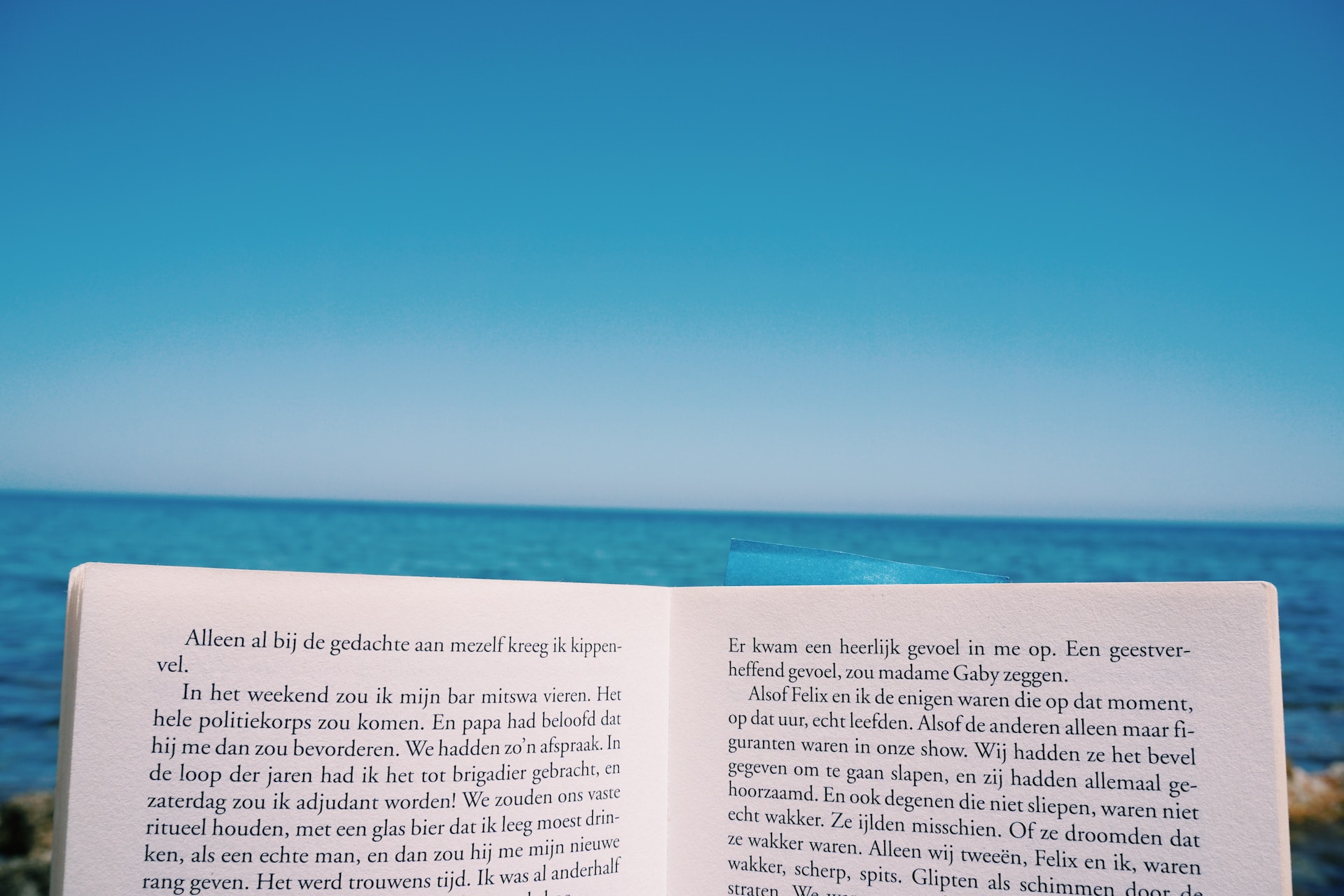人間は忘れる生き物。
どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。
それは読書も同じこと。
読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。
ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、現役のライターである著者が、現場で15年かけて蓄積した「話し言葉から書き言葉へ」のノウハウと哲学を、余すところなく伝えている“書く技術”の授業です。
この本の第一目標は「話せるのに書けない!」を解消すること。
私たちは、人に口で伝えることはできても、それを頭の中で文章に変換しようとすると、とたんに固まってしまいます。
なぜなのか。
それは、「話すこと」と「書くこと」が、まったく別の行為だからです。
ところが、学校の授業では、“文章の授業”が行われていません。
“書く”という行為の意味や意義、具体的な技法にまで踏み込んだ授業が行われてはいないのです(作文は形を変えた“生活指導”であって、“文章の授業”ではありません)。
自分の思いを「言葉だけ」で伝える“書く技術”。
文章を書く機会が増えていく時代に、“書く技術”は一生使える“武器”になります。
本書では、学校では教えてくれなかったホンモノの文章力、思考のメソッドを手に入れるための技術が解説されています。
基本情報
・タイトル :20歳の自分に受けさせたい文章講義
・著者/編者:古賀 史健(著)
・発行日 :2012年1月25日
・ページ数 :280p
・出版社 :星海社
【 読書メモ 】
■ 文章とは、頭のなかの「ぐるぐる」を、伝わる言葉に“翻訳”したもの
・文章を書こうとすると固まってしまう人は、頭のなかの「ぐるぐる」を整理できていない状態
・自分の気持ちをうまく文章にできない人は、「ぐるぐる」を“誤訳”している状態
・書く=翻訳する(整理・再構築し、アウトプットする)ことは考えることであり、理解したから書くのではなく、書くことにより理解できる
・“翻訳”の基礎練習は、聞いた話を誰かに話すこと(再構築・再発見・再認識の習得)
■ 文章は「リズム」で決まる
・論理破綻した(=前後の文がつながらない)文章は、リズムよく読めない
→論理破綻を回避するには「文と文のあいだに接続詞が入るか」確認する
・文章の「視覚的リズム」:圧迫感を解消する
①句読点の打ち方:1行の間に必ず句読点をひとつは入れる(文字間の圧迫感を解消)
②改行のタイミング:最大5行あたりをメドに改行する(行間の圧迫感を解消)
③漢字とひらがなのバランス:ひらがな(白)のなかに漢字(黒)を置く(字面が持つ圧迫感を解消)
・文章の「聴覚的リズム」:音読して自分の文章に客観性をもたせる
①自分の意図する箇所に読点「、」が入っているか確認する
②言葉の重複を確認する
・断定の切れ味は、文章にリズムを持たせる(ただし、断定する箇所の前後をしっかりとした論理で固める必要がある)
■ 文章の面白さは「構成」で決まる
・実務的文章や小論文などで広く使われている「序論・本論・結論」に、映像表現のカメラワークを取り入れる
①序論=導入:客観のカメラ(遠景)。客観的な状況説明をおこなう
②本論=本編:主観のカメラ(近景)。序論に対する自分の意見・仮説を語る
③結論=結末:客観のカメラ(遠景)。再び客観的な視点で論をまとめる
・原稿用紙5枚以下に収まるコンパクトな文章(日常文)の導入は「映画の予告編」
→予告編がつまらないと観てもらえない(読んでもらえない)
[予告編の基本パターンは3つ]
⑴インパクト優先型:冒頭に強めの結論(一見ネタバレだが、前後の文脈を断ち切ればOK)
⑵寸止め型:核心部分を観客に想像させる(ギリギリまで情報開示するのがポイント)
⑶Q&A型:問いと答えが揃っている(本編を見てもらえなくても要点は伝えられる)
・構成は「眼」で考える
①頭のなかの「ぐるぐる」を図解・可視化で客観視し、「流れ」と「つながり」を明確にする
②文字量を「眼で数える」習慣をつくる(「序論2:本論6:結論2」あたりの割合が適当)
■ 「論理的な文章(理にかなった文章)」は、3層のマトリョーシカ構造になっている
1.大マトリョーシカ=主張:「結局なにが言いたいんだ?」に“ひと言”で答えられるもの
2.中マトリョーシカ=理由:主張を訴える理由
3.小マトリョーシカ=事実:理由を補強する客観的事実
→マトリョーシカのように、「主張」の人形を開けると「理由」が、「理由」を開けると「事実」が入っていない場合、中身のスカスカの主張になる(事実→主張→理由の構成も可能)
■ 読者の「椅子」に座り、同じ景色を見ることで、読者を理解することができる
・あらゆる文章の先に読者がいる(私的な日記でさえ“自分”という読者がいる)
・本当の意味で「同じ椅子」に座れる読者は、2人だけ
①10年前(あの時)の自分:10年前の自分に語りかけるように書く
→いま、この瞬間にも日本のどこかに「10年前の自分」と同じ問題を抱えている人は必ずいる
②特定の“あの人”:多数派ではなく、特定の“あの人”に絞り込んで書く
→“みんな”から喜ばれようとするほど、誰からも喜ばれない文章になる
・椅子に座る「たったひとり」以外の第三の読者(例えば自分の親)でも理解できる文章を書く
・読者の「自分事」になる書き方をする(読者は「他人事」「正しいだけ」では動かない)
①独自の“仮説”を提示し、読者に問いかけ、一緒に検証する
→「起“転”承結」で興味を引きつけ、読者を巻き込む
◇冒頭に「自らの主張と真逆の一般論」をもってきて、“転”で仮説や疑問を提示する
②文中にツッコミ(反論)を入れ、それに答える(再反論を加える)ことで、読者と“対話”する
③細部の描写を丁寧にする(誤情報をなくす)ことでリアリティを生み、読者にも“体感”させる
■ 読者が文章(ノンフィクション)に求めているのは3つの要素
1.目からウロコ:目が覚めるような読書体験「ええーっ!!」(全体の3割)
2.背中を後押し:自説を補強しようとする自己肯定欲求「そうそう」
3.情報収集:冷静で客観的な意見を求める欲求「なるほど」
■ 推敲の基本は、ハサミを使った編集
・書きはじめの編集
①頭の中のぐるぐる(多すぎる元ネタ)を可視化する
◇テーマに関連したキーワードを書き出す→キーワードの傾向をつかむ→その傾向以外のキーワードを書き出す
②可視化した“広範な元ネタ”から「何を書かないか?」を考える
・書き終えてからの編集
①「(せっかく書いたのに)もったいない」を退け、文章を削る
②長い文章は短い文章に切り分ける(リズム感・意味の通りをよくする・結論がわかりやすい)
③論理性のチェック:書いた文章を図解できるか?(矢印でつながるか、順番がおかしくないか等)
④細部の描写チェック:書いた文章を読んで“映像”が思い浮かぶか?
⑤最低でも2回は読み返す(書く自分、読み返す自分、もう一度読み返す自分の3人でチェックする)
■ 「いい文章」とは「読者の心を動かし、その行動までも動かすような文章」のこと
・読者を動かすには、自分の“思い”を知り、それを「言葉だけ」で正しく伝えることが必要
=必要なのは、“翻訳”の意識と技術だけ(文才は不要)
・才能(文才に限らず)を問うのは「言い訳」:才能や文才を気にせず、とにかく書くことで前に進む